◆ ◆ ◆ 唯識の世界 ◆ ◆ ◆
12.煩悩の原泉―末那識
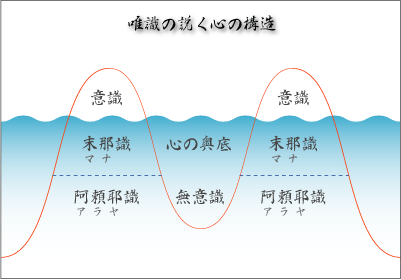
唯識が無意識層の心として提唱した末那識(まなしき)は、恐らく人間以外の動物には考え難(がた)いものだと思われます。末那識は他動物には無い『煩悩』を生み出す原泉であるからです。この末那識は、図に示しますように、阿頼耶識の上層にあると唯識は考えていますが、末那識は阿頼耶識の中に見出せる"生きようとする本能、生命を維持しようとする意志"を原泉として、人間に固有な無意識の心としてしかも独立的に位置付けたところに、欧米深層心理学には無い唯識の特徴があると思います。
そして、この煩悩を湧き出(い)だす末那識は、人間を苦悩し続けさせるのでありますが、一方、この末那識があるからこそ、真理に目覚めたいと言う欲求が生まれ、そして信心の世界、悟りの世界へ導かれると言ってよい、と私は思います。そして、この末那識は阿頼耶識と異なり、生まれながらに持っている"こころ"゛ではなく、人間に生まれてから形成されるもので、成長するに従ってその存在感をいよいよ増してゆくものではないかと考察しています。産まれたての赤ん坊は、阿頼耶識は持っていても、煩悩の原泉たる末那識は未だ芽吹いていないと考えてよいのではないかと思います。
さて、末那識は、無意識に自分に執着する心と言い換えられます。そして、この心は、四六時中働いていると唯識は考えます。寝ている時も、気を失っている時にも、であります。前にも喩えとして申し上げましたが、多人数で撮った同窓会やクラスの集合写真でも、或いは数人で撮った家族写真を手渡された時でも、誰もが例外無く、先ず最初に自分を確認して、それから他の人物に目が移って行くのが普通であります。たとえ恋人と写っていても、たとえ最愛の孫達と写っていても、先ずは自分を確認することから始まるはずであります。これ、無意識の心である末那識が働いているからであると、唯識は考えるのであります。
ここで末那識に関する説明を太田久紀師の著書から抜粋致します。
人間はどのように存在しているかという点を掘り下げたのが阿頼耶識であったのに対し、末那識は阿頼耶識の上に働き、阿頼耶識に関わってゆく歪ん(ゆがん)だ生命の動きを掘り下げたものである。末那識の"末那(マナ)"とは、梵語の「マナス」というのを音写したものである。その点、梵語の「アーラヤ」を"阿頼耶"と書いたのと同じやり方である。マナスとは「思い量る(おもいはかる)」という意味なので"思量"識ともいい、"こころ"を表わす心・意・識という語を厳密に使い分ける場合には"意"を当てる。
では、「思い量る」というのは、何を思い量るのであろうか。末那識が思い量るのは、自分の都合である。ただひたすら自分のことだけを思い量り、何事も、自分中心に考えるのである。前にも一度紹介した良遍の著書『法相二巻抄(ほっそうにかんじょう)』には、
凡夫の心の底に常に濁りて、先の六の心はいかに清くおこれる時も、我が身我が物と云う差別の執を失せずして、心の奥は、いつとなくけがるる如きなるは、この末那識のあるによりてなり。などといわれている。的確に簡潔にまとめられた名文であろう。とにかく、末那識は、ただひたすら自分を愛着し耽着して、他を認めたがらぬ我執の"こころ"である。
末那識は・・・・ひがめる心なり。
末那は、阿頼耶の見分にむかいて、これを、我、我と思う。この外に物を知ることなし。
―引用終わり
自分中心の心が"末那識"であり、この末那識の自己中心性を4つに分析したのが、根本煩悩と言われる、我癡、我慢、我見、我愛であります。
この4大根本煩悩から、六つの煩悩、そして、二十の随煩悩が生まれると唯識は見ています。我々を苦悩させる末那識の正体を次項で、煩悩の全てを明らかにしたいと思います。