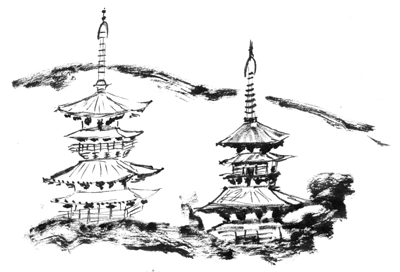掬水月在手
『水を掬(きく)すれば、月、手に在り』
路傍の野草に宿る一滴の露に宿る月の光と同様に、仏様の慈悲の光は地上の生きとし生きる一切のものに注がれている。生まれ難い人間に生まれ、遭い難き仏法に出遭え得た今生だからこそ、本来自己の心の中に宿っている光(仏心)に気付きたいものです。
「水を手にすくえば、遠く光輝くお月さんも手の中にあるではないか、それと同じように仏法の悟りも遠くに求める必要は無いのだ、我が心の中に本来具わっている仏性に気付けばよいことなのだ。しかし、水を手にすくおうとする意思即ち悟りを求める心(菩提心)が無ければ何も得られないのだ」と言うことだと思う。
本来具わっていることに気付くと言うことを青山俊董尼が次のような喩えで説明されています。
『たとえばリンゴの落ちるのを見てニュートンは引力を発見した。ニュートンが引力を発見してから引力が働き出したわけではない。ニュートンが発見するしないにかかわらず。引力は始めから存在しているのであり、科学の眼をもったニュートンにはそれが見えた。科学の眼を持たないわれわれには、おそらくリンゴが落ちたことしか見えないであろう。見えないものにとっては無いと同じである。だからといって引力の働きを頂いて地上に張り付いておられることにおいては、ニュートンと少しも変わりはないのだが。
積極的に求めることにより本具(ほんぐ)の命の尊さに目覚めよ、その呼びかけが「水掬すれば月手に在り」の一句の心といえよう』